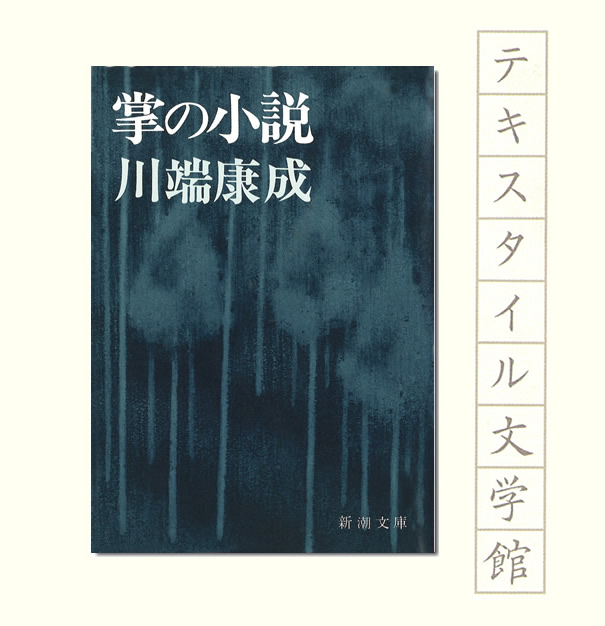
『掌の小説』より「小切」川端康成 著
テキスタイル文学館
その襦袢は美也子が十三、四のころ着ていたもの。色があせ、一人前になったいま着るには袖幅も足りなくなっていました。しかし洗って鏝(こて)をあて、寸法を確かめると、工夫すれば大丈夫―。そう思った彼女は布切を詰めた箱を座敷に開けて、袖を接ぐのに使えそうなものを探し始めました。
淡い思い出をまとった布を、膝が埋もれるほどに広げながら、美也子は少女時代の友だちのことを思い浮かべます。その子の親は娘の成長を記録するのに、生まれたときからの着物の小切を、写真帖のように貼って残しているのでした。それがうらやましくて、家に帰った美也子は自分も作ってほしいとねだります。それを聞いて母は思いもつかなかったと感心しますが、なぜか父は怒りだしました。
人の思い出は幸せなものばかりではありません。生きて時間を重ねていく中で、大きな悲しみや苦労を背負うこともあります。不安な時代の中で大人になった彼女は、父の言わんとしたことが何となく理解できるようになっていました。
そんな思いに浸っているところに、母がやって来ました。彼女は娘が襦袢を縫い直そうとしているのを見るや、大きな葛籠(つづら)を持ってこさせ、今度はその中から布を見繕い始めます。その間、母と娘で交わされた短い会話。言葉の隙間を埋めるのは、言葉に出さない種々の思いでした。


