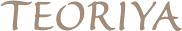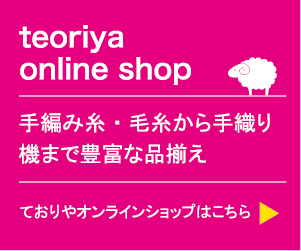コットン(綿糸)の魅力
2025/03/15

繊維長の差が用途を分ける
コットン(綿糸)は、すぐれた通気性と吸水性を特徴とする、衣服や日用アイテムに広く使われているおなじみの素材です。
その原料は、アオイ科ワタ属の植物が作る「蒴果(さくか)」の繊維、いわゆる「綿花」。その繊維の長さによって、短繊維綿(繊維長21ミリ以下)、中繊維綿(21~28ミリ)、長繊維綿(28ミリ以上)に分類され、それぞれの特徴を生かして糸が作られます。
生産量が最も多いコットンは中繊維綿で、手編み・手織り糸はもとより、シャツやジーンズ、タオルなどポピュラーなコットン製品に広く使われています。
それよりも繊維が短い「デシ綿」などは、それだけでは糸にしづらいこともあり、繊維の長い種類と混ぜ合せたり、太く短い繊維の弾力を生かしてふとん綿が作られたりしています。

繊維長の差が品質を分ける
綿花のグレードは、繊維が長く細くなるにつれ上がります。「ギザ45」や「ギザ70」などのエジプト綿、ペルー原産の「ピマ綿」を改良した「スピーマ綿」、カリブ産の「海島綿(かいとうめん)」といった品種の繊維長は35ミリ超え。これら長繊維綿の中でも特に長い繊維をもつものは「超長綿」と呼ばれています。生産量が少なく値も張りますが、しなやかで光沢感のある上質な糸が作られ、さらにそれを織った高品質なテキスタイルも製品化されています。
わずか数ミリの繊維長さの違い。それが、コットンの品質・用途に大きな違いを生んでいるのです。
お店でも「エジプト綿ギザ45」や「シルキーコットン」などエジプト綿を使用した糸を販売。手ざわりがよく美しい糸として人気の商品です。
日本の職人さんたちの知恵
いま日本で栽培されている綿花はごくごくわずか。原料のほとんどは海外からの輸入に頼っています。だから栽培国の気候や情勢に左右されることもしばしば。
その中で安定した品質の糸を作り続けるために、いろんな個性をもった綿花をブレンドし、それぞれの「良いとこ取り」をする方法が定着しています。
このような方法を採る国は、世界的に見ると少数派。日本の職人さんたちの知恵が、コットン糸作りにも生かされているのです。
ておりやブログ『コットン糸(綿糸)のバリエーション|3種類の繊維の長さと加工法』でより詳しくご覧になれます。ご興味のある方は是非ご覧ください。
ておりや通信『te』vol.66 「糸と手しごとファイル」より
関連記事
- 2025.7.18 ブログ, ニュースクリップておりや通信【te】ニュースくりっぷ|砂漠の国でも愛用されてきたコットン
- 2018.7.20 糸のこと, つくること肌にやさしいコットンの2重織りマフラー
- 2018.5.14 糸のことコットン糸(綿糸)のバリエーション|3種類の繊維の長さと加工法
- 2025.3.5 『te(て)』記事より美しい光沢、なめらかな感触…「プラチナ」を思わせるウール誕生
- 2024.5.13 『te(て)』記事より2025年春夏まで続くファッショントレンドに「手仕事感」
- 2025.2.5 『te(て)』記事より赤穂緞通(あこうだんつう)―咲きつなげられる伝統の華―